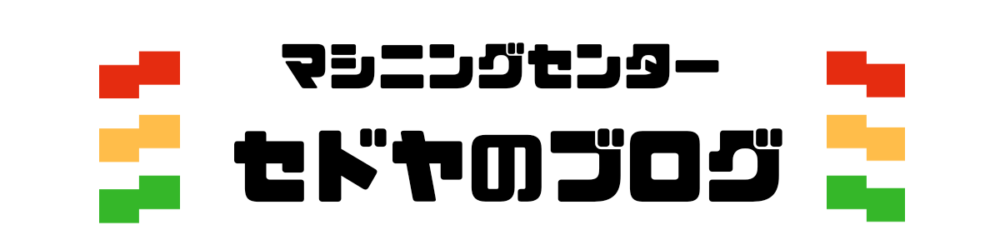この記事は
そういう人たちに読んでいただきたくて、機械加工を始めた人が悩む「びびり」の原因と対策についてまとめました。
この記事を読むと、「びびり」の原因に対して適切な対策ができるようになります。
「びびり」の発生の要素として3つあります。
- 工具
- 被削材
- 工作機械
これらのどれが「びびり」の原因かを特定して、対策します。
「びびり」の原因の特定する方法
「びびり」は振動で、強制びびり振動と自励びびり振動があります。
強制びびり振動は、強制振動源による振動で、フライス加工の断続切削、または、機械のモータや歯車、ポンプなど外部の振動です。
自励びびり振動は、切削加工中の抵抗の変化などで 生じた振動が収まらない場合に起こる振動で、いったん発生すると工具や被削材などの振動の伝達特性と連なって大きな振動になることが多いです。
「びびり」が生じやすい状況を挙げていきます。
- 切削条件が悪い、工具が長い、刃数が多い
- 被削材が振動しやすい
- 機械の剛性不足、老朽化、機械のクセ
普段から使っている工作機械の場合、原因は予測できるようになります。機械のクセがわかるまでは、振動がどこから発生しているかを、音や触ったりして確かめます。
工具の「びびり」対策
フライス加工の場合、断続切削になるため、切れ刃が接触するたびに振動が発生します。
びびったら試す3つの「びびり」対策
- 切削抵抗の低い工具を使う
- 回転速度、送り速度を変える
- 切込み量を減らす
長い工具を使う場合
剛性の高い工具を使う
超鋼素材の工具や、干渉のない程度の太いホルダー、アバーを使う。
切れ刃の角度を変える(高送り用工具など)
高送り用工具は荒加工用ですが、切れ刃の角度が緩やかなので切削抵抗が軸方向(Z方向)に強くなり「びびり」を抑えられます。
不等ピッチ、不等リードの工具を使う
不等間隔の工具には、自励びびり振動の抑制効果があります。
正面削りやエンドミルで側面加工の場合の「びびり」対策用の工具です。
「びびり」の抑制機能を持ったホルダーを使う
大昭和精機(BIG)では防振機構を内蔵されたスマートダンパーがあります。
私も使ったことがありますが、「びびり」は大幅に低減します。
他のメーカーでも防振工具を発売しています。詳しくは「防振工具」で検索してみてください。
刃数が多い場合
刃数が多いと「びびり」やすくなります。
刃数の少ない工具にするか、切込み、回転数で調整すれば「びびり」は抑えられます。
刃数を増やせば送り速度が上がりますが、「びびる」ので切込みが少なくなります。トレードオフの関係です。
切削時の摩擦が原因の場合
切削時の摩擦で「びびり」がでる場合は
- 切れ刃を新品に交換
- 接触面の少ない切れ刃の工具を使う
- 切削液を使う
これらの切削抵抗を少なくさせる対策が有効です。
被削材の「びびり」対策
被削材が振動に弱いと「びびり」の原因になります。手やハンマーでたたいて、振動が止まるまで時間がかかるようだと段取りを補強する必要があります。(切削条件の変更で「びびり」が止まることもあります)
薄板の正面削り場合は、両面同時フライス加工すると「びびり」に強いですが、特殊な工作機械になります。
大型の被削材や製缶品など複雑な形状の場合、補強が難しい場合が多いです。事前に段取りができるよう準備しておきましょう。
機械の「びびり」対策
工作機械が原因で「びびり」が起こることもあります。
- 工具の取り付け面が劣化して工具の装着が不安定
- 機械の据え付け状態が悪い
- 機械内部の部品に問題がある
これらの原因の場合は修理することになります。また、工作機械の特定の場所で加工したとき「びびり」やすいなど、機械のクセや構造が原因と思われる場合もあります。
古い工作機械に起こりやすいので、定期的なメンテナンスで予防することができます。
まとめ:「びびり」の原因、対策
まず試す3つの「びびり」対策
- 切削抵抗の低い工具を使う
- 回転速度、送り速度を変える
- 切込み量を減らす
一般的に、びびり対策で回転数を下げますが、上げることで「びびり」が抑制されることもあります。私の場合は、まず回転を上げてみて「びびり」が改善されなければ下げていきます。試してみてください。
工具に原因がある場合は、
- 切れ刃の角度を緩やかなものに変える
(高送り用工具など) - 不等分割ピッチ、不等リードの工具を使う
- 刃数を少くする
- 防振機能のついたホルダーに換える
これらを組み合わせたりして対策しましょう。
被削材が原因の場合は段取りを補強し、工作機械が原因の場合は修理です。
以上です。
参考にしていただければ幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。